今の時代、運営するビジネスが順風満帆で何の問題もないという会社はごく一部です。
中小企業も大企業も、大なり小なり経営上の問題を抱えているところがほとんどでしょう。
特に現在はコロナ禍ということで、売り上げの減少を実感している事業者様が多いと思われます。
今回は赤字経営に関してどのように考えればよいのか、複数の側面から見ていきます。
赤字になっても必ずしも危険とは限らない

ビジネスを立ち上げて間もない方や、経験が少ない経営者の場合、赤字=危険、赤字=悪と捉えるかもしれませんが、実は必ずしもそうとは限りません。
具体的な社名は挙げませんが、有名な大企業でも赤字状態で経営を続けているところは結構あります。
赤字といってもその原因はいくつか考えられ、一時的に支出が収入を超えてしまっても、必ずしも危険信号というわけではないのです。
例えば売り上げが減少したため、新たなサービスを生み出すために経費をかけた結果、数字的に赤字になることはあります。
しかしその投資の結果、新たな需要を生み将来の収入が増えれば会社はつぶれることはありません。
重要なのは中長期的な回転資金のキャッシュを確保できているかどうかです。
会社経営には収入と支出の両側面がありますが、支出の面で必要なキャッシュが枯渇すると会社は一気に倒産します。
この点、黒字経営であっても回転資金のキャッシュの確保に失敗する例もよくあり、これを黒字倒産といいますね。
赤字であっても中長期的に回転資金が枯渇しないようにできれば、会社がつぶれることはないので安心してください。
そうは言っても、赤字よりは黒字の方が良いに決まってるでしょ?と思われるかもしれませんね。
確かに、黒字倒産とならないように配慮していれば、赤字よりは黒字の方が安定した企業経営ができます。
ただ、赤字には実はメリットもあることをご存じでしょうか?
メリット狙ってあえて赤字経営路線を取る経営者の方もいるくらいです。
次の項では赤字のメリットについて見ていきます。
赤字経営にはメリットもある

赤字になってしまった企業には主に税務面で優遇されるメリットがあります。
赤字の企業が優遇されるのは、国力の源である企業がつぶれてしまわないよう、国が救済措置を施すからです。
例えば、経営上で利益が出るとその利益の度合いに応じて法人税がかかりますが、赤字経営で数字上の利益が出ていない場合、法人税は最少額の7万円(住民税均等割り)で済みます。
また赤字の場合、その損失を翌年以降に繰り越して使うことができる大きな利点もあります。
これは例えば今年赤字で来年黒字になった場合、来年の黒字と今年の赤字を相殺して黒字の儲けを数字上減らし、その分の税負担を下げる効果があります。
法人で青色申告の場合、欠損金の繰越控除という仕組みにより、平成20年4月1日までの欠損金は7年間、それ以降の欠損金は9年間繰り越すことができます。
仮に赤字の年度の翌年がまた赤字でも、上記の期間はその赤字を利用できるのでかなりお得です。
個人事業で青色申告の場合は純損失の繰越控除という仕組みにより、赤字の年度の翌年以後3年間の繰り越しが可能です。
法人よりは繰り越せる期間が短くなりますが、それでも大きなメリットになります。
このように赤字には一定のメリットもあるわけですが、やはりデメリットもあります。
赤字のデメリット
経営者としては精神衛生上よろしくないというデメリットがあるとして、実務面では赤字経営となることで銀行が融資に及び腰になるというデメリットが考えられます。
必要な場面で十分な資金調達ができなければ、運転資金の枯渇により倒産の心配が出てきます。
我々が手掛けるファクタリングであれば売掛先の信用を見るので、赤字経営であっても特段問題がないのですが、貸し付けを行う銀行はそうではありません。
資金を欲する企業自体に信用がないと当然及び腰になりますから、赤字は企業の見栄えに影響することは否めません。
長期目線で赤字の解消ができるかどうかがカギ
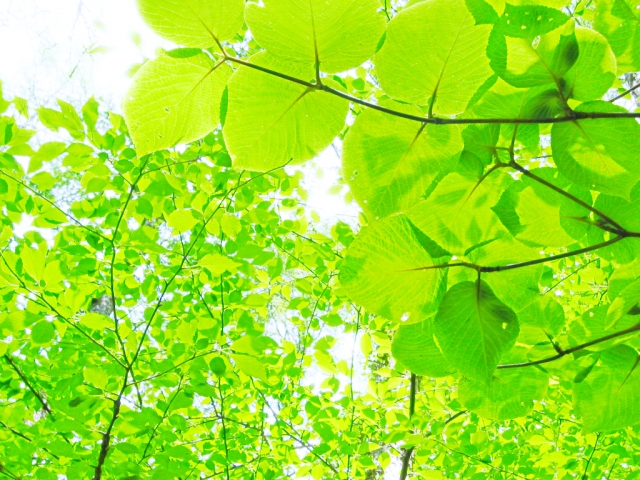
赤字であっても必ずしも危険とは言えないものの、倒産を避けるには中長期的に見て売り上げが回復し、赤字を脱することができるかどうかの見極めが重要になります。
これこそがまさに経営者としての手腕であり、売り上げの減少があればこれを回復させる期待が持てるか、何らかの施策を打って売り上げ回復を実現できるかどうか思案が求められます。
昨今はコロナ事情という非常に特殊な環境下にあるため、見通しが利きづらい状況にあります。
慎重に検討した結果、売り上げ回復は望めないと判断すれば、現事業からの早期撤退という選択もあり得ます。
コロナで変化した需要に訴求する新たなビジネスに転換するのも一手ですから、経営者として柔軟に、臨機応変に立ち回っていく姿勢も必要かもしれません。


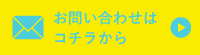
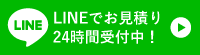



















この記事へのコメントはありません。